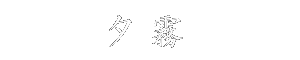
(9)
「殺すのか…?」
驚いて訊き返したサスケに、カブトは頷いた。
「心配しなくても大丈夫だよ。何の証拠も残さずに、病死に見せかけて殺せる薬がある」
養父もそれで『眠らせた』と、内心でカブトは思った。
「…あの人はずっとイタチのツーマンセルのパートナーだったんだ。それを殺すなんて……」
「イタチ君を奪われても良いのか?」
サスケは改めて、カブトを見た。
カブトは狡猾だ。
見ていもしない事をでっち上げて、鬼鮫を始末する口実にしようとしているのかも知れない。
そして鬼鮫殺しの罪をサスケ一人に被せて、イタチがサスケを嫌うように仕向けようとしている可能性もある。
カブトの言葉を信じてイタチを疑うなど愚かだと、サスケは思った。
何より、愛する者を取り戻す為とは云え、恋敵を暗殺するような卑劣なマネはしたくない。
「…今はまだ何もするな」
「屈強な男を病死に見せかけて殺すには時間がかかるんだよ?のんびり構えているうちに逃げられたらどうする」
「伊織は保育器から出てまだ二ヶ月だ。とても連れて歩けるような状態じゃない」
だから暫くは猶予がある筈だと言ったサスケに、カブトは幽かに眉を顰めた。
「連れて行く積りなら…ね」
「イタチが伊織を置き去りにする筈が無い」
「どうしてそう、言いきれる?抜け忍に取って赤ん坊はかなりの負担だし、鬼鮫と逃げるなら、君の子供は邪魔だろう?」
「あんなに可愛がっているのに、見棄てる訳が無い」
それはどうかな、と、カブトは言った。
「可愛がっているとは言っても、世話は医療忍たちに殆ど任せきりじゃないか」
娘の世話を医療忍に任せるようとイタチを説得したのは他ならぬ自分とサスケだと判っていながら、敢えてカブトは言った。
「それに夜中にまで様子を見に行っているのも、長く一緒にはいてやれないから、今の内に出来るだけの事をしてやりたいと思っているだけかも知れないよ?」
「…イタチの事を何も知りもしないで、勝手な事をほざくな」
怒鳴りたい気持ちを必死に抑えて、低くサスケは言った。
カブトは、口元に幽かな笑みを浮かべた。
「そう。僕はイタチ君の事を碌に知らないし、知らないのだと自覚している。だからあらゆる可能性を冷静に検討できるんだ。だけど君はどうなんだ?イタチ君への感情で理性が濁って盲目になっているんじゃないのか?」
「…っ…」
反論できず、サスケは歯噛みした。
イタチの本心が判らずに苛立ち、猜疑心に囚われ、悩んでいるのは事実だ。
やはりもう一度、イタチと会って、冷静に話すべきだとサスケは思った。
感情に流されては、何もかもぶち壊しにしてしまいかねない。
サスケは椅子の上で座りなおし、一呼吸置くと、『大蛇丸』らしく不敵な笑みを浮かべた。
「…病死になど見せかけなくとも始末する手段なぞいくらでもあるわ。ただ、命令を下すのは私よ。勝手なマネは赦さない」
「……御意」
反論を諦め、カブトは深く一礼した。
「『大蛇丸』様」
その夜、イタチの部屋に行こうとしていたサスケを呼び止めたのは鬼鮫だった。
「……何か用かしら?」
「是非ともお耳に入れたい事があります__イタチさんの事で」
矢張りカブトの言葉は本当だったのかと、サスケは思った。
感じたのは嫉妬や憤りよりも、奇妙な寒々しさだ。
「……手短にね」
言って、サスケは踵を返した。
「今日、イタチさんの本心をやっと訊き出せましたよ」
大蛇丸の部屋に入ると、鬼鮫は言った。
サスケは変化を解き、鬼鮫に向き直る。
「あの話は……忘れてくれと言った筈だ」
「イタチさんを譲る積りは無いと私も言いましたよね__古寺で」
覚えていますか?と鬼鮫に問われ、サスケは渋々、頷いた。
「それでも私が身を引こうとしたのは、それがイタチさんの為だと信じたからですよ。イタチさんもアナタを愛していて、アナタと添い遂げるのが何よりもあの人の望みなのだと思ったから」
「……違うとでも言うのか…?」
死刑宣告を受けるような気持ちで、サスケは訊いた。
鬼鮫はやや間を置いてから、続けた。
「勿論、愛してはいるでしょう。さもなければアナタの犯した罪を負ったりはしなかったでしょうから」
ただそれは、と、鬼鮫は言った。
「あくまで兄弟、兄としての愛情です」
「だったら何で1年前のあの夜、オレを拒まなかった?恋人だったアンタを隠れ家から追い出してまで、どうしてオレを受け入れた?」
「罪悪感です」
「……罪悪感?」
鸚鵡返しに、サスケは訊き返した。
鬼鮫は頷いた。
それから、木の葉にいた頃の事を覚えていますか?と問う。
「暗部にいた頃のイタチさんが、任務で返り血を浴びて帰って来た夜の事、覚えていますか?」
「勿論、覚えている…。イタチがオレの記憶を操作していたんだとアンタに聞かされてから記憶操作の作用が弱まったらしく、昔の事は殆ど思い出した」
「ではその後毎晩、アナタがイタチさんの帰りを寝ずに待っていた事も?」
鬼鮫の言葉に、古い記憶がサスケの脳裏に蘇った。
あれはシスイが『自殺』した事件のあった後で、あの頃のイタチは家族とも碌に口をきかなくなり、笑うことも無くなっていた。
それでただでさえ兄の身を案じていたところに、血だらけで帰って来たイタチの姿を見たのだ。
イタチが死んでしまうのではと思い、母親に必死で助けを求めた時の事を、今でも鮮やかに覚えている。
返り血だと判っても安堵は出来なかった。
イタチは人形のように虚ろな眼をして、その身体は氷のように冷たかったからだ。
「…あの頃のイタチさんがどれ程、辛い想いをしていたかは、私よりアナタの方が良くご存知でしょう?」
鬼鮫の言葉に、サスケは黙ったまま小さく頷いた。
あの時にはまだイタチの身体の秘密は知らず、一族の者達がイタチをどんな眼で見ているか知ったのも後になってからだ。
だがイタチが酷く傷ついている事は、6歳の子供でも判った。
次の日に、明け方まで兄の帰りを待ち、冷たい手を温めながら「兄さんが無事で良かった」と言った時、イタチの漆黒の瞳から透明な滴が零れ落ちた。
兄が泣くのを見たのは初めてだった。
強くていつも冷静な兄が声も無く泣く姿にサスケはどうして良いか判らず、ただ抱きしめて幼子をあやすように宥めた。
イタチが涙を見せたのはその夜、一度きりだったが、その後もイタチを放っておくことが出来ず、毎日、帰りを待ち続けた。
初めのうちはただ、兄の無事を確かめられればそれで満足だった。
だがその事をきっかけにイタチと過ごす時間が増えると、もっともっとイタチと一緒にいたいと願うようになった。
それまでは素っ気無かった兄が優しくしてくれるのが嬉しくて、手の届かないところにいるのだと思っていたイタチを、初めて身近に感じることが出来た。
今にして思えば、あの頃が一番、幸せだったのかも知れない。
「イタチさんは精神的にとても強いものを持っている人で、それは幼い頃から変わらないのでしょう。それでも人間です。深く傷つき、独りで耐え切れなくなる時もある。誰かの救いを必要とする時が」
「…10年前のあの頃が、そうだったんだろう」
「だから救いの手を差し伸べたアナタに縋った。無論、誰でも良かった訳では無いでしょう。兄のように慕っていたシスイから裏切られたせいで、警戒心も強くなっていた筈ですから」
だから、と、鬼鮫は続けた。
「血を分けた実の弟であり、まだ6歳の純真な子供だったアナタを信頼したんですよ。そのアナタから恋心を打ち明けられた時は、さぞかし心外だったでしょうね」
------お前も俺の身体が目当てだったのか?
想いを打ち明けた時のイタチの言葉が、サスケの脳裏に浮かんだ。
イタチは憤り、暫くは口もきいてくれない程だった。
その頃のサスケはシスイがイタチにした事を知らなかったから、イタチがそこまで怒る理由が判らなかった。
ただ誤解されたのが哀しくて、その誤解を解きたくて必死だった。
「…イタチは、オレがあいつが両性具有だと知って、あいつの身体に興味を持ったんだと誤解したんだ。だが誤解はすぐに解けた。オレが兄弟として以上にあいつの事を大切に想っているんだと、その気持ちを理解してくれた」
「でもイタチさんに取っては、アナタはあくまでも弟なんですよ__あの頃も、今も」
「イタチが……そう、言ったのか?」
サスケの問いに、鬼鮫は頷いた。
「そんな話は嘘だ。あの頃のオレ達は……ただ添い寝だけしてた訳じゃない」
サスケの言葉は、鬼鮫にはやや驚きだった。
イタチには、木の葉にいた頃のサスケとの関係は深いものではなく、小鳥のような口づけを交わすだけの淡いものだったと聞いていたからだ。
「……アナタは6歳か7歳だったのでしょう?」
鬼鮫の言葉に、サスケは気色ばんだ。
「…確かに、最後までは出来なかった。オレはまだ子供すぎて、気持ちばかりが急いてどうにも出来なくて……」
------すぐに大人になるから。それまで待っていて
必死の思いで言ったサスケにイタチは優しく微笑み、「身体の関係などなくとも恋人同士にはなれる」と言った。
あの時のイタチの美しさは忘れられない。
「でもあの時、イタチは確かに、オレを恋人なんだと認めてくれた」
「……それは、イタチさんがアナタを必要としていたからですよ」
気持ちが重苦しくなるのを感じながら、鬼鮫は言った。
イタチが自分に全てを打ち明けたのでは無かったという事より、サスケのイタチへの一途な想いを目の当たりにして、それを打ち壊そうとしている自分に後ろめたさを覚える。
だがこのままの関係が続けば、イタチはずっと罪悪感に苛まされ続けるのだ。
「あの頃のイタチさんには支えが必要だった。それを失う訳には行かなかった。アナタの恋心を心外に思っても、それを拒む事は出来なかったんですよ」
「だからオレを……騙していた…と?」
「それが、イタチさんの罪悪感の理由です」
back/next
|
|