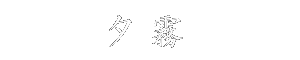
(8)
「…自分が両性具有だと気づいた事、しかもそれを一族の皆に知られてしまった事は、俺にとって文字通りの悪夢だった」
視線を落としたまま、呟くようにイタチは言った。
「それに無抵抗の女子供を殺めなければならないような暗殺任務にも中々、慣れなくて、ただ自分の感情を殺すのに精一杯だった…」
無理も無い、と、鬼鮫は思った。
殺戮を楽しむ自分ですら、無抵抗の相手を殺すのは後味が悪い。
ある程度、強い相手と戦って斃すからこそ、己の強さを感じ、陶酔にも浸れるのだ。
増してや無用な殺戮を好まないイタチの事。
暗殺任務の残酷さに心を痛めていた事は容易に推測できる。
「俺は幼い頃からずっと一族の皆に期待され、その期待に応えるのが当然だと思ってきた。期待に応える事に、誇りすら感じていた。だが実際には……体よく利用されていただけだ」
鬼鮫は黙ったまま、イタチが続けるのを待った。
「あの頃、暁にいた大蛇丸は俺と一族の不和をどこかから嗅ぎ付けたのか、俺に里抜けを勧めてきた。自分を貶める一族の為に利用され続ける気は無かったが、里を裏切るのは抵抗があった。それならば、いっそ自らの身を処する方が増しだと…」
「…死のうとしていたんですか?」
訊いた鬼鮫に、イタチは曖昧に首を振った。
「『死ぬ』という感覚では無かった。俺は一族の隆盛の為の道具でしか無かったのだ。その道具に『欠陥』が見つかり、一族はそれをどうするかで揉めていた。自分の一族のそんな無様な姿を見続けるくらいならば、終わりにしてしまおうと思っただけだ」
それに、と、幾分か苛立たしげに髪をかきあげ、イタチは続けた。
「暗部の同僚何人かから言い寄られて…俺の身体の秘密が一族以外にも漏れているのでは無いかと危惧した。人の口に戸は立てられない。秘密が広まるのを防ぐには、俺自身が消えるしか無かった」
鬼鮫はイタチの肩に置いた手に、わずかに力を込めた。
イタチのようにプライドの高い人間が貶められ、劣情の対象として見られるのがどれ程、苦痛だったが、想像に余りある。
両性具有だと知られるまでは生まれながらの天才として期待と賞賛を一身に浴びてきたのだから尚更、屈辱だっただろう。
自分自身を物のように感じるところまで追い詰められていたのだと思うと、憤りよりもむしろ口惜しさを感じる。
イタチがそれ程、苦しんでいた時に、自分は何もしてやれなかった。
まだ出会ってもいなかったのだから当然の事なのだが、それでも何の力にもなれなかった事が口惜しい。
「…だが俺は死ねなかった。まだ…生に執着があったらしい。或いは__大蛇丸の誘い通りに里を抜けて、俺を貶めた一族が慌てふためく姿を見たかったのかも知れない……」
生きる意味を見失い、死ぬ機会も得られず、ただ命じられるままに任務に赴き、人を殺める__
イタチが任務で返り血を浴びて家に戻ったのは、そんな日々の繰り返される中の或る夜の事だった。
サスケはイタチが酷い怪我をしたのだと思い込み、泣き喚かんばかりに心配した。
「その時、俺は気づいた。一族の中にも、まだ俺の身体の秘密を知らず、俺に憧憬と羨望の眼差しを向ける者が残っているのだ…と」
兄の身を心配したサスケは、次の日からイタチが任務から帰るのを寝ずに待つようになった。
任務の終わる時間は不規則で、明け方になる事もあったが、それでもサスケは待った。
時には待ちくたびれてイタチのベッドで眠ってしまう事もあったが、イタチが帰ってくればすぐに眼を覚まし、無事を確認した。
そしてその後は温めあうようにして抱き合い、共に眠った。
「何の為に任務をこなすのか、何の為に生きるのかその意味を失っていた俺に、サスケは生きる理由を与えてくれた。サスケの超えるべき壁であり続ける事__その為ならば、俺は里に残り、生き続けようと思った」
「……お察ししますよ」
イタチは振り向き、鬼鮫を見上げた。
その漆黒の瞳に挑むような光があるのを、鬼鮫は認めた。
「俺はサスケを失いたくなかった。いずれサスケが俺の身体の秘密を知って、他の者たちの様に俺を蔑むようになるのは耐えられなかった。だから出来るだけの時間をサスケと共に過ごす事に割いて、サスケを……懐柔しようとした」
言って、イタチは踵を返し、鬼鮫から離れた。
「…サスケは純粋で素直な子だ。そしてずっと俺に憧れていた。嫉妬もしていたが、それでもサスケの目標が俺である事は変わらない。だからサスケを手懐ける事など容易かった__容易すぎた」
「……でも、それと恋とは別でしょう?」
「ああ…。別だ」
だが、と、イタチは続けた。
「サスケはまだ幼く、その違いに気づかなかった。そして、俺に恋をしているのだと信じ込んだ。俺は……そんなサスケの幼さに付け込んで、俺の事だけを考えるように仕向けた。あの頃は、どうしてもサスケを失いたく無かったからだ…」
鬼鮫は口を噤んだまま、イタチの後姿を見つめた。
人の心など計りがたいものだ。
時には自分の気持ちすら判らなくなる。
サスケのイタチに対する想いはイタチの言うとおり、憧れを恋慕と履き違えただけのものかも知れないし、誤解しているのはイタチの方かも知れない。
イタチがサスケを必要としたのは、溺れる者がただ藁を掴もうとしただけかも知れないし、本人が気づいていないだけで恋だったのかも知れない。
だが、今はそんな事はどうでも良い。
はっきりしているのは、イタチがサスケとの関係で悩み、苦しんでいる事。
そして自分はまだイタチを愛し、取り戻したいと願っている事……
「__それで、どうする積りなんですか?」
暫くの沈黙の後、鬼鮫は訊いた。
「このままあやふやにサスケさんを拒み続けていたら、サスケさんは納得しないでしょう。辛いでしょうが、態度をはっきりさせなければ」
イタチは鬼鮫を見、何も言わずに視線を逸らした。
鬼鮫はゆっくりと相手に歩み寄り、背後から包み込むように抱きしめた。
そして、耳元で囁く。
「私はずっとあなたの側にいますよ。何があろうとずっと…」
イタチは瞼を閉じた。
サスケと再会した夜の事が脳裏に蘇る。
古寺で共に過ごした日々。
木の葉の里での思い出。
------オレはあんたの為に皆を殺したんだ……!!
殆ど反射的に、イタチは眼を開けた。
そして改めて思った__自分がどれ程、サスケを追い詰めてしまったのかを。
「……もう暫く様子を見て、伊織に重い障害が無いと判ったら__」
「サスケさんの記憶を操作して、サスケさんとお子さんを木の葉の里に帰しますか?」
鬼鮫の言葉に、咽喉が締め付けられるような息苦しさをイタチは感じた。
だが鬼鮫の言う通り、今のこの不安定な状態を続ける事は、サスケの為にも伊織の為にもならない。
イタチはもう一度、眼を閉じ、「ああ…」と呟いた。
そしてその場から気配も無く立ち去った者の存在に、二人とも気づかなかった。
「何か用か?」
部屋を訪れたカブトに、サスケは無愛想に訊いた。
大蛇丸の姿に変化してはいるが、口調を真似る気にはならない。
もう、何日もイタチに会っておらず、日に日に会いたいという気持ちが募る。
だが日が経てば経つほど会いに行き難く感じられて、自分の気持ちを持て余していた。
「…干柿鬼鮫の事だけど」
口を開いたカブトを、サスケは見た。
カブトは眼鏡の位置を直し、続けた。
「かつて大蛇丸様はイタチ君が君と鬼鮫とに二股をかけているのだと仰っていた。僕にはそんな事は信じられなかったが……どうやら事実だったようだね」
「…何だと?」
カブトは肩を竦めた。
「イタチ君が鬼鮫と一緒にいる姿を、たった今、この眼で見たんだよ」
「今は二人で修行をしている筈__」
「抱きしめて耳元で囁くのが修行か?」
相手の言葉を遮って、カブトは言った。
自分が苛立っている事に気づき、そんな自分に苦笑する。
落ち着け、と、自らに言い聞かせながら、愕然とした表情を浮かべるサスケを見下ろした。
「君が最近ずっと苛立っていたのは、彼が原因なんだね?」
サスケは答えず、歯噛みした。
矢張り鬼鮫に相談したのは間違っていた。
それとも、最初から自分は道化でしか無かったのか?
「…今は嫉妬よりも何よりも、対策を講じるべきだ」
サスケの座っている側に歩み寄り、机に手を付いて、カブトは言った。
「対策だと?何であんたがこんな事に首を突っ込む?」
「決まっているだろう?君が、『大蛇丸』様だからだよ」
サスケは言い返そうとして口を噤んだ。
自分たちの関係を知られてしまった事は不本意だが、これ以上、隠すのは無理だ。
「イタチ君が鬼鮫と子供を連れてこの里を抜けでもしたら、君はここに留まってはくれないだろう?そして『大蛇丸』様がいなくなれば、音の里は内紛に見舞われ、いずれ滅んでしまうだろう」
「イタチは……鬼鮫さんと何を話していたんだ?」
「こちらに気づかれないだけの距離を保っていたから会話の内容までは判らなかったけれど、かなり深刻そうだったよ」
サスケは溜息を吐き、視線を逸らした。
イタチは元々、サスケと子供を木の葉の里に帰らせる積りだった。
そんな考えはとっくに捨てたものだと思っていた。嫌、思いたかった。
自分がどれ程イタチを愛し、イタチを必要としているか、理解してくれたのだと信じていた。
或いは、『理解』はしているのかも知れない。
ただイタチは、自分を必要とはしていないのだ。
「…それにしても意外だったよ。まさかイタチ君が、本当に二股かけていただなんて」
「そんな言い方は止めろ」
「だったらどういう事なんだ?君はずっとイタチ君に復讐しようとしていたんじゃないのか?それなのにイタチ君との間に子供を為し、イタチ君を助ける為に大蛇丸様に自らの身体を差し出した。ところがそのイタチ君は、子供を産んで三ヶ月にしかならないのに、他の男の腕に抱かれている。これは一体、どういう事なんだ?」
訊きたいのはオレの方だ__サスケは言いかけた言葉を噛み殺し、ゆっくりと息を吸い、そして吐いた。
それから、まっすぐにカブトを見据える。
「…あんたがイタチに横恋慕してるのは知ってる」
「それは__」
「だが今は嫉妬より、対策を講じるべきだ」
カブトは口を噤み、サスケを見た。
そしてもう一度、眼鏡の位置を正す。
「…取るべき手は、一つだけだよ」
「この里から追放するのか?」
「そんな事をしたら逆効果だ」
口元に薄い哂いを浮かべ、カブトは続けた。
「眠らせるのさ__永遠に」
back/next
|
|