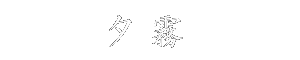
(13)
「そんな姿でうろうろ歩き回らないでくれ。誰かに見られたらどうする積りなんだ?」
大蛇丸に変化しない姿のままで部屋に戻るサスケの後を追いながら、カブトは言った。
サスケに受けた傷は自ら医療術で治癒させたが、痛みは残っている。
「…オレに煩く説教するな。もう一度、千鳥を喰らいたいか?」
「君は全てをぶち壊しにする気か?」
掴まれた腕を反射的に振り払おうとして、サスケは思いとどまった。
イタチの哀しげな顔が脳裏に浮かび、そして消える。
「……何故だ……?」
「サスケ君…?」
「あいつはオレの全てなのに…どうしてイタチはそれを信じてくれない?オレ達の間には娘までいるのに、どうして他の男なんかに……」
握り締めた拳を振るわせるサスケを、カブトは黙って見つめた。
そして、愚かしい、と思った。
人は勝手に期待なぞするから、勝手に傷つくのだ。
自分の感情ですら時に制御しきれなくなる時があると云うのに、他者の気持ちを思いのままになど出来るはずが無い。
だが人間という生き物は愚かしく、貪欲だ。
恋人の誠意を、家族の愛を、仲間の信頼を、あたかも当然であるかの如く期待し、そして『裏切り』に傷つく。
誰も信じなければ傷つく事も無いのに、信じる事を止められない。
だがそれでは、と、カブトは思った。
少なくとも、忍としては失格だ…と。
「あの野郎…イタチの為とか言いながら、イタチを奪い返す機会をずっと窺ってやがったんだ」
低く、呪うようにサスケは言った。
「『奪い返す』?と、言う事は要するに__」
「あの男とイタチは恋人同士だった__1年前までは」
相手の言葉を遮って、サスケは言った。
カブトは幾分か驚いた。
「つまり……君は他者(ひと)の恋人を奪って、孕ませたという訳なのか?」
「オレ達はそのずっと前から恋人同士だった…!」
握り締めた拳で机を叩き、サスケは言った。
机の表面に、亀裂が走る。
カブトはひと呼吸置いてから、サスケに向き直った。
「…ずっと前と言うのは、イタチ君が里抜けする前の話かい?」
「……そうだ…」
半ば唖然とした気持ちで、カブトはサスケを見つめた。
大蛇丸から聞いた話によればイタチが里抜けしたのは13の歳で、その時、サスケはまだ8歳かそこいらだった筈だ。
それに、二人は血の繋がった実の兄弟だ。
どれ程、仲が良かったとしても、それはとても恋などとは呼べまい。
だが今は、サスケに話を合わせてやらなければならないのだと、カブトは思った。
「でも判らないな…。恋人同士だったのなら、何故、君はイタチ君に復讐しようなどと思ったんだ?」
サスケはすぐには答えなかった。
自分が作った机の亀裂を見つめ、口を噤む。
やがて、独り言のように呟いた。
「…イタチはオレの記憶を操作し、オレの罪を負って里を抜けたんだ……」
「記憶操作?」
「……うちは一族を滅ぼしたのは__オレだ……」
「……イタチさん……?」
鬼鮫は黙ったまま佇むイタチに、そっと声をかけた。
「風が冷たくなってきましたよ。そろそろ部屋に戻った方が……」
イタチはやはり何も言わない。
鬼鮫は相手に歩み寄り、イタチに触れようとして思いとどまった。
ただ、黙ったままイタチを見守る。
「……鬼鮫…」
やがて、イタチは相手の名を呼んだ。
「…何ですか?」
「いつか、お前は自分が捨子だったと言っていたな。自分を棄てた両親を恨んでいた…と」
鬼鮫は頷いた。
「育てられないのなら、殺してくれた方が良かったと思った事もありましたよ」
でもそれは、と、鬼鮫は続けた。
「私が育てられた施設が酷い所だったからです。もしあなたが、伊織さんを手放すことを躊躇っているのなら__」
「判っている」
相手の言葉を遮って、イタチは言った。
「『母親』が両性具有で両親が実の兄弟であるなどという状況が、伊織の為にならないのは火を見るより明らかだ。それに…俺は両親と縁が薄かった。いずれにしろ、良い親になどなれそうにない」
「…縁が薄いとは、つまり…?」
「俺はうちは一族の後継者として、アカデミー卒業まで親元から離されて長老たちの家で育てられた。代々うちはの当主を継ぐ者は皆、同じだ。そこでは子供扱いもされず次期当主として傅かれる一方、常に忍らしく冷静である事を要求された」
鬼鮫がイタチと初めて会った時、イタチはまだ13の子供だった。
だが寡黙で冷静で、子供らしいところが少しも無いのに驚いたものだった。
初めの内は自分の一族を皆殺しにしたくらいなのだから、どこか普通ではないのだろうと思っていた。
やがてツーマンセルのパートナーとしての信頼が築かれるようになると、イタチは鬼鮫の前で無防備な寝顔を見せるようになった。
その思いがけない無垢さに心を動かされた時の事は、今でも鮮やかに覚えている。
正直に言ってと、イタチは幽かに口元を綻ばせた。
「幼い頃のサスケが母上に甘えている姿を見て、俺は驚いたものだ。こんな軟弱者が、忍になれるのか…と」
イタチの口元の笑みは消え、憂いが残った。
「伊織を手元においたところで、どう接して良いのか俺には判らない。赤子のうちならばともかく、成長して自分の母親は誰なのか、俺が伊織に取って何者なのか問われるようになったら……」
鬼鮫はイタチの腕にそっと触れた。
「…木の葉に戻れば、サスケさんに好意を寄せる女性は沢山いるでしょうからね。サスケさんはきっと優しくて愛情に満ちた人を選んで、伊織さんを幸せにするでしょう」
「……そうだ…な」
疼くような胸の痛みを持て余しながら、イタチは言った。
「君が、うちは一族を…?」
信じられない思いで、カブトは訊き返した。
うちは一族殲滅の事件があったのは今から8年前。
サスケは8歳になったかならないかの頃だ。
「…集会に一族全員が集まる機会を利用して、毒を盛った。死体に偽装して死因を撹乱したのは、イタチだ」
「どうしてそんな事を…?」
「詳しい事情まで、アンタが知る必要は無い」
苛立たしげに、サスケは言った。
「イタチはオレの為に自分一人で罪を負おうとして、オレの記憶を操作した。それでオレはずっとあいつに復讐しようとしていたが、1年前の夜、イタチとあの男が一緒にいるところを見てしまって……」
「嫉妬の余り、記憶操作が解けた……という訳か」
サスケは幽かに頷いた。
その場でただちに術が解けた訳では無いが、そこまでカブトに話す気は無い。
あの夜の光景を思い出すと、今でも嫉妬で虫唾が走るようだ。
カブトは口を噤み、サスケを見遣った。
イタチが元々鬼鮫と恋人同士だったのなら、今の二人の関係も理解できる。
それにサスケの恋情は、かなり一方的なもののようだ。
イタチもサスケを拒まなかったのだから憎からずは思っているのだろうが、添い遂げる積りまでは無かったのだろう。
ところが懐妊してしまい、その上、体調を酷く崩して身動きが取れなくなった。
仕方なく子供を産むまではサスケと一緒にいようと思い、鬼鮫もその条件付きで同意したのだろう。
それならばサスケと娘を木の葉の里に帰らせようと考えるのも当然だ。
だがそうなれば音の里は求心力を失って崩壊し、自分の居場所がなくなってしまう。
そんな事はさせられないと、カブトは思った。
「…鬼鮫の存在があっては、君はイタチ君の心を取り戻せそうには無いね」
カブトの言葉に、サスケは睨むように相手を見た。
カブトは笑った。
「安心して良いよ。君の望みは、僕が叶える」
back/next
|
|