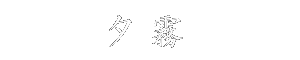
(12)
「…それは聞き捨てならないね」
眼鏡の蔓に軽く触れて、カブトは言った。
「安心しろ。オレはイタチと一緒で無ければ木の葉に帰る積りなんぞ、無い」
「一緒に…は無理だろうね。いくらうちは一族の末裔でも、その一族を殲滅した張本人なら、極刑は免れない」
でも、と、カブトは続けた。
「判らないな。イタチ君が君を愛しているなら、どうして君や娘と離れようなんて思うのだろう」
「…それがオレと伊織の為だと、あいつは信じているからだ。重い障害が残るなら別だが、伊織は木の葉で暮らした方が幸せだと__」
「障害が残るなら別?」
相手の言葉を遮って、鸚鵡返しにカブトは言った。
「つまり、娘に重い障害が残るようなら、イタチ君は君と共に音の里に居続ける積りなんだね?」
一瞬、空気が凍るような間があった。
次の瞬間、サスケはカブトの襟首を掴んでいた。
「てめぇ…伊織に何かしやがったら殺すぞ…!」
「落ち着いてくれ、サスケ君。そんな風に殺気を放ったら、警護の忍が駆けつけて来かねない」
薄笑いを浮かべたカブトに、サスケは思わず歯軋りした。
それから、突き放すようにして手を離す。
「…僕はただ状況を確認しているだけだよ。確かに自立した生活も出来ないくらいの重い障害が残るようなら、専属の医療忍に手厚く看護されるここの環境の方が、君たちの娘の為になるだろうからね」
「だがそうでなくとも…イタチと伊織は一緒に暮らした方が幸せな筈だ」
「でもイタチ君は自分が両性具有だと知られるのを酷く嫌悪している。それにとてもプライドが高い。今までずっと男として生きて来たのに、母親だとは名乗れないんじゃないのか?」
サスケは溜息を吐きかけ、それを何とか噛み殺した。
イタチは望んで妊娠した訳では無かった。
母親になる積りなど、もとより無かったのだ。
伊織を愛しているだけに、側にいながら母だと名乗れないことに罪悪感を抱くかも知れない。
それにイタチが言っていた通り、伊織には友や師が必要だろう。
だが伊織は、自分とイタチとを繋ぐ絆なのだ。
手放す事など出来ない。
だからと言ってイタチを繋ぎとめる為に伊織を傷つけるなど、考えただけで吐き気がする。
「…もう一度、言っておく。伊織に何かしやがったら、てめぇを生かしてはおかない」
カブトは大袈裟に肩を竦めて見せた。
「『大蛇丸』様のご命令が無ければ、僕は何もしやしないよ。ただ__」
幾分か声を潜めて、カブトは続けた。
「干柿鬼鮫。彼は早急に処分してしまうべきだ。イタチ君が君と娘を木の葉に帰らせようとしているのも、彼の入れ知恵かも知れない」
「…貴様の指図は受けない」
だったら、と、幾分か苛立たしげにカブトは言った。
「行って自分の眼で確かめてくるが良い。今、イタチ君と鬼鮫が、何をしているのかを」
「……鬼鮫…?」
苦笑した鬼鮫の名を、怪訝そうにイタチは呼んだ。
鬼鮫は何と言うべきか迷いながら、黙ってイタチを見つめた。
イタチがこれほど思い悩み、眠れぬ夜を過ごすのは、サスケへの強い想いの現われに他ならない。
かつて幼いサスケを篭絡し、それゆえに弟の一生を狂わせてしまったのだという罪悪感は確かに深いのだろうが、イタチもサスケを愛しているのだから、そのままサスケの想いを受け入れれば良いだけの筈だ。
だがイタチは、サスケの側にいて不安定になるのが激しい恋の故だとは気づいていない。
初めてイタチと肌を交わした夜、不安の余り一睡も出来なかった事を、鬼鮫は思い起こした。
何年も密かに想い続け、とうてい手の届かない高嶺の花なのだと諦めていた相手が自分の腕の中で眠っている事が、どうしても信じられなかった。
イタチが自分に身体を赦したのは単なる気まぐれか純粋な性欲処理に過ぎず、翌朝には何事も無かったかのように振舞うのではないかと思うと、眠ることが出来なかったのだ。
イタチが今、抱いているであろう恐れは、あの頃の自分のそれとは異なるのだろう。
だが相手を強く愛し、欲するが故の不安定な感情である点は同じだ。
それは幼い頃から天才と目され、常に冷静に任務をこなしてきたイタチには理解し難い感情なのだろう。
「…判らないなら教えて差し上げます。あなたは、サスケさんを失うのが怖いんですよ」
「……」
前夜の夢が脳裏に蘇り、イタチは何も言えずに鬼鮫を見つめた。
眼を逸らすことすら出来ない。
「あなたはプライドが高く、ご自分では気づいていないかも知れませんが、独占欲が強い。だから一度(ひとたび)サスケさんの想いを受け入れたら、サスケさんの心変わりには耐えられないでしょう。でもサスケさんはまだ16の少年で、そんな幼い恋など淡く移ろいやすい」
鬼鮫の言葉に心臓を締め付けられるように、イタチは感じた。
「それにあなたは優秀な忍として幼い頃から常に冷静である事を自らに課していた。だから、身を焦がす程の恋に溺れて自分を見失ってしまう事は、プライドが赦さないのかも知れない」
イタチはゆっくりと眼を閉じた。
鬼鮫の言葉を否定したくとも、咽喉を締め付けられているようで声が出ない。
「あなたが私を選んだのは、私が決してあなたを裏切らないと判っているからと、そして__」
一旦、言葉を切り、それから鬼鮫は続けた。
「あなたの私への感情は、サスケさんに対する想いのように激しくは無いからですよ」
「そんな事は……」
眼を開け、抗議するように言ったイタチに、鬼鮫は幽かに笑った。
「あなたの私への想いが偽りだと言いたいのではありません。あなたのような人が、何の愛情も感じていない相手に身体を赦すとは思えませんから。それに、冷静さを欠いて眠れぬ夜を過ごす程に感情的になる事ばかりが、本物の恋だと言うわけでも無いでしょう?」
イタチは何も言わなかった。
ただ黙ったまま、視線を落とす。
「揺ぎ無い信頼と、深く変わる事のない愛情__あなたは私にそれを求め、私を生涯の伴侶にと選んだ。そして私は、あなたの望みを叶える為ならば何でもすると誓います」
鬼鮫はイタチに歩み寄り、そっと腕に触れた。
「サスケさんと離れる事は、確かにあなたには酷く辛い事でしょう。でも時が経てばその傷は癒える。ですがサスケさんと共にある事を選べば、あなたはこれからもずっと不安や嫉妬、そして罪悪感に苛まされ続けなければならない…」
鬼鮫は俯いたままのイタチの頬に軽く触れた。
そしてイタチが拒まないのを確かめてから、抱き寄せる。
「サスケさんと別れる辛さは、私が忘れさせてあげますよ。木の葉にいた頃の辛い思い出も、何もかも……」
囁くように言って、鬼鮫はイタチを強く、そして優しく抱きしめた。
そして、しなやかな髪を撫でる。
「それにあなたも仰っていた通り、辛い過去を捨てて木の葉に帰った方が、サスケさんも幸せでしょう。あなたが一族殲滅の罪を負ったのは、サスケさんの為だったのでしょう…?」
「俺…は……」
自分が手にかけた者たちの死に様に半ば呆然とし、両親に止めを刺す事が出来ずに泣いていたサスケの姿がイタチの脳裏に蘇った。
里の治安を守り続けてきた誇りある一族の名を持つ者として、その一翼を担おうと夢見ていたサスケに一族殲滅の咎を犯させた罪は、サスケを愛することでは消せまい。
罪を贖う為には、サスケを過去の軛(くびき)から解放してやるしか無いのだ。
イタチが躊躇いながら相手の背に腕を回した時、空気が凍りついた。
「……サスケ……」
大蛇丸に変化もしていない姿で現われた弟の名を、イタチは呟くように呼んだ。
鬼鮫はイタチを庇うように、サスケとの間に割って立つ。
そしてそれが一層、サスケの憤りと嫉妬を煽った。
抑え難い殺気が、周囲の空気を振るわせる。
「止めるんだ、サスケ君…!こんな所で事を起したら他の部下たちに__」
「やかましい…!」
蒼白い閃光と共にカブトの身体が宙を飛び、そのまま地面に叩きつけられた。
鬼鮫は鮫肌を持って来なかった事を後悔した。
まるで、1年前にサスケと会った時と同じだ。
イタチは身構えた鬼鮫の腕に軽く触れると、そのまま前に進み出た。
「サスケ……」
静かに名を呼び、歩み寄る。
それから、サスケを抱きしめた。
「憎むのなら俺を憎め。殺すのなら俺を殺せ。お前に殺されるのならば……本望だ」
「イタチ……」
身体から力が抜けるのを、サスケは覚えた。
そして何も言わずイタチの手を振り払い、踵を返した。
back/next
|
|