裏切ったのは、あの人ではない
裏切ったのは、己の未熟な自我
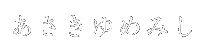
−(3)−
「…本当にアナタって真面目ですねえ…」
情事の熱が醒めるとすぐに刀の手入れを始めたイルカを横たわったまま見上げ、ぼやくようにカカシは言った。
「刀はきちんと手入れをしておかないと切れ味が鈍って使い物にならなくなりますからね」
「だから俺は忍刀よりクナイの方が好きですけどね。色々と便利に使いまわせるし」
ゆっくりと上体を起こすと、カカシはイルカと背中合わせに座り、幾分か体重をかけて寄りかかった。
温もりを心地よく感じながら、傍らに置いてあったイルカの暗部面を手に取る。
白地に朱と墨とで模様の入った鳥の面。
幽かな違和感に、カカシは眉を顰めた。
「…カカシさん。こっちに来るなら来るで、連絡してくれても良かったじゃないですか」
「…俺が暗部に戻るって知らなかった?」
「部隊長から聞いて知ってましたよ。でも俺は…出来ればあなたから知らせて欲しかった」
少し拗ねたような恋人の言葉に甘えを感じ取って、カカシは口元を綻ばせた。
「知らせようとは思ったんですよ。でもそうしてたら、アナタまた、任務に私情を挟むなって怒ったでしょ?」
「__それは……」
こちらを振り向き、意外そうに目を見開いた相手に、カカシは軽く笑って見せた。
「アナタの側にいたくて、綱手さまに直談判したんです。勿論、五代目にはもっともらしい口実しか話してませんけど」
「……俺の、為に…?」
「アナタと、アナタを愛してやまない俺の為に」
カカシの言葉に、イルカは幽かに頬に血を昇らせ、照れたように笑った。
その笑顔を見られただけでも暗部に戻った甲斐があったと、カカシは思った。
元々、イルカを穢れない天使か何かだと思っていた訳ではないのだ。
ただイルカが暗部の任務に罪悪感を覚え、苦しむことになるのを憂えていた。任務は任務とイルカが割り切れるなら、それで良い。
裏切られたように感じるなどお門違いだ。
イルカが平然と人を殺せる人間だと判った今でも、イルカが唯一の安らぎである事に変わりは無い。
「…面が少し、汚れてしまいましたね」
イルカの面を見つめながら、何気なくカカシは言った。
血痕を洗い流したような古い染みと、細かい傷がいくつもついている。
もう一度、違和感にカカシは眉を顰めた。
「汚れているのは当然ですよ。古いものですから」
「…古いって……」
「その面は、父親の形見なんです」
幽かに指が震えるのを、カカシは感じた。
改めて、イルカの父親の物だったという暗部面を見つめる。
他の鳥面とは僅かに意匠が異なる、独特な品だ。
「__これは…まさか、鵺…?」
「さすが、よくお判りですね」
言って屈託無く笑ったイルカの顔を、カカシは正視できなかった。
『鵺』は、大名の屋敷などに潜入して暗殺を行う専門の部隊だ。
暗部の中でも特に、暗殺に特化した者たちの部隊だと言える。
追い忍として抜け忍を始末するのも『鵺』の仕事で、噂では暗部内の内通者を探り出し、処刑するのも『鵺』だという。
ひとたび『鵺』となった者は『人』には戻れない__まだ少年だったカカシに『鵺』の事を話した男は、そう言って嗤った。
つまり俺たちは、まだ『人』に戻れる事になっているらしい。とても信じられないが…と。
「……アナタのお父さんが暗部だったなんて知りませんでした」
「言ってませんからね…。カカシさんにはいつか話したいと思っていたんですけど、きっかけが掴めなくて」
イルカは手入れの終わった刀を鞘に収めると、カカシに向き直った。
「俺の母親も暗部__『鵺』だったんです。だから俺は以前からずっと暗部配属願いを出していて…今やっと、希望が叶ったんです」
「……」
「カカシさんにも以前から憧れていました。長い間、暗部の第一線で活躍して、戦果を上げている忍だって噂を聞いて」
カカシは、すぐには何も言えなかった。
「……つまりアンタは、俺が暗部出身だから__」
幽かな鳥の鳴き声に、カカシは口を噤んだ。
襖を開けると、遣い鳥が舞い込んで来る。
「……任務の様です」
「…お気をつけて」
自分を見送るために立ち上がったイルカの方を見もせずに、カカシは部屋を出た。
夜の明ける気配を感じ、イルカは幽かに溜息を吐いた。
夜半にかけての任務は明け方までに終わるのが通例だ。待っている積りではなかったが、何となく目が冴えて眠れなかった。
両親が『鵺』だったと打ち明けた時の、カカシの表情を思い出す。
人形のように整った顔は、人形のように無表情だった。
暗部に入れば、本当の意味でカカシに近い存在になれるのだと、そう思っていた。配属を希望したのは両親のような忍になりたいという強い想いがあるからだが、時折、感じていたカカシとの間の溝が埋まることを期待していたのも事実だ。
カカシは暗部出身のエリート上忍で、自分はしがない中忍のアカデミー教師。
何気ないカカシの言葉や態度に劣等感を感じ、苛立つこともある。
カカシが自分を相手にしているのはほんの気まぐれで、飽きれば離れて行ってしまうのではないかと、不安になる時もある。
だから、少しでもカカシに近づきたかった。
暗部での実戦を経験すれば、カカシも任務のあとに黙り込むだけでは無くなるのではないかと期待していた。
暫くの間、カカシと会えなくなるのは辛かったが、それ以上に得るものがあるのだと信じていたのだ。
だが、カカシは不機嫌になっただけだった。
わざわざ火影に直談判までして暗部に戻ったのだと聞いた時には嬉しかった。それなのに、両親の事を話しただけであんな態度を取るなんて思ってもいなかった。
「……やっぱり…俺の側にいたくて暗部に戻ったなんて嘘なんですね……?」
イルカはもう一度、溜息を吐いた。
任務はもう終わっている筈だが、待っていてもカカシは帰ってこないだろう。
「…少しでも眠らないと…」
自分に言い聞かせるように呟いて、イルカは目を閉じた。
next
|