あの時のあいつは
死にたがっているかの様だった
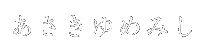
−(1)−
動くたびに脇腹から血が滲み出すのを感じ、カカシは内心、毒づいた。止血しても止まらぬ血の臭いは敵を引き寄せる。まるで、自分の居場所を宣伝しているようなものだ。
今回の奇襲は明らかに失敗だった。
どうやら暗部内に内通者がいるらしい。こちらの動きは完全に予測され、トラップを仕掛けられた上に敵に囲まれてしまった。
カカシが自ら囮役を買って出て仲間は何とか逃がしたが、カカシ自身は窮地に陥っていた。腕と脇腹に怪我を負い、敵に追われている。
その上、面ごと顔を叩き斬られ、左目が見えない。
先に逃れた仲間が応援を送ってくれる事だけが唯一の頼みの綱だが、自分の居場所を仲間に知らせる為に式を召喚するチャクラも残っていない。
痛みと出血と熱のせいで精神の集中もままならず、意識が半ば朦朧としている。
__これまでか…
カカシが覚悟を決めた時、闇の中を影が動いた。
影は鮮やかな動きで敵を倒し、カカシに走り寄る。
『大丈夫か?』
『オビト…』
親友の狐面に安堵したのも束の間、すぐに敵の攻撃を受ける。
何とかかわしたが、思うように身体が動かず、かわすのが精一杯で反撃できない。
『ここは俺に任せて逃げろ』
『オビト、だが__』
『すぐに他の仲間も来る。行け!』
不本意ながら、カカシは頷いた。
今の自分の状態では足手まといなだけだと判断したのだ。
『…この借りは後で必ず』
『水臭いな。お互い様だ』
面の下でオビトが笑ったのが、カカシには判った。
カカシは身を翻し、残った僅かなチャクラを利用して樹に駆け登った。枝から枝へと飛び移って逃げる内に、足首を掴まれて引きずり降ろされ、地面に叩きつけられる。
『…ッ…貴様は…!』
相手は、暗部の装束を身に着けていた。今回の奇襲部隊の一人、カカシもよく知っている男だ。
お前が内通者か__カカシが思うのと、斬りつけられたのが殆ど同時だった。
そして、二人の間にオビトが割って入ったのも。
『__オビト……』
カカシを庇って背中を斬られたオビトの身体が、力を失って動けずにいるカカシの上に折り重なる。
喉がひりひりするような、強烈な鮮血の匂い。
そして、経験した者だけに感じ取れる、死の匂い。
狐面の下から流れ落ちた熱い血の、鮮やかな紅。
「オビト……!」
ベッドの上に跳ね起き、カカシは肩で息をした。
全身を脂汗が濡らし、まるで負傷して血を流しているような錯覚を覚える。
思わず隣に手を伸ばし、そして今は独りなのだと、改めて思い知った。
両手で顔を覆い、溜息を吐く。
暗部時代の記憶は、忘れかけた頃に夢となって現れる。
負傷して動けず、敵味方の屍骸が腐っていくのを見つめている夢。
自分が殺した敵の屍体に、どこまでも付き纏われる夢。
洗っても洗っても浴びた返り血が落ちず、川が血に染まるのを為すすべも無く見遣る夢……
他の夢は実際にあった事でもなく抽象的なのに、オビトが死んだ時の夢だけは酷くリアルだ。内通者の面の模様まで、はっきりと夢に出てくる。
けれどもオビトの名を叫んだ後の事は何も覚えていない。
後から駆けつけた仲間に助けられた時、錯乱状態でオビトの手当てをしてくれと喚いていたらしい。
オビトから離れようとせず、傷の手当てが遅れて危険な状態だったと、後で聞かされた。
カカシはベッドを出、風呂場に行って冷たいシャワーを浴びた。
オビトが死んだ直後の事は何も覚えていない筈なのに、オビトの血が熱かった事と、その身体が冷たくなっていった感触は覚えている。
こうしていくら冷たいシャワーを浴びても、その感触と、オビトの流した血の匂いは身に纏わりついて消えない。
大丈夫ですか…?
こんな時、イルカがいれば優しく抱きしめてくれた。
濡れた髪も拭かぬまま、カカシはベッドに仰向けに横たわり、ここにはいない恋人を想う。
俺が、側にいますからね…?
イルカの身体の温もりは、オビトの身体の冷たさを忘れさせてくれた。
血の匂いも。
死の匂いも。
「……イルカ先生がいなくなった途端にこれだなんて……」
カカシは口の端を歪めて笑い、今は側に居ない想い人を求めるように、シーツの上に指を這わせた。
「俺にはこんなにもアナタが必要なのに」
暗い天井を見つめながら、カカシは呟いた。
アナタは……俺がいなくても平気なんですか……?
「大分、慣れたみたいだな」
任務をこなした後、刀の手入れをしているイルカに、部隊長が声をかけた。
「有難うございます。でも、外の任務は久しぶりなので、矢張り緊張しますね」
「正直言って、何年も内勤だった奴が暗部で使いものになるのか疑問だったが…矢張り、血は争えないな」
イルカは微笑した。
実のところ、自分でも不安はあった。修行は常に怠らなかったから腕が鈍っているとは思わなかったが、実戦の場から離れて3年も経っているのだ。
今は、前線の緊張感がむしろ心地良い。
流石に上忍と同レベルというのは無理だが、トラップに関する専門的な高い能力を持つ者として仲間にも受け入れられている。
アカデミー教師の仕事は気に入っていたし、性に合っているとも思っていた。
だが今は、教師の仕事から得るのとは全く別種の達成感と充足感を感じる。
あそこはアンタみたいな人に耐えられる所じゃ無い
不意に、カカシの言葉が脳裏に蘇り、イルカは幽かに眉を顰めた。
カカシが心配してくれる気持ちは嬉しい。けれども、暗部の任務に耐えられないと言われたのは心外だった。
忍としてのカカシの強さには憧れる。
時折、垣間見せる子供のような態度には愛しさを覚える。
けれども、いかにもエリート上忍然とした物言いには、時として苛立ちを感じる。
カカシにそんな積りが無いのは判っていても、どうしても中忍の自分が見下されているように感じてしまうのだ。
それでも、こうしてカカシの側を離れていると、やはり寂しい。
知り合って僅か数ヶ月。恋人同士と呼べる関係になってからまだ日が浅い。
そんな時に離れてしまうのは寂しくもあり、不安でもあった。
だが、任務は任務。
私情を挟むわけには行かない。
「そう言えば、イルカ。お前、『写輪眼のカカシ』と親しいらしいな」
部隊長の言葉に、イルカ頬に血が昇るのを感じた。
だがどうやら、部隊長の言葉に深い意味はないらしい。
二人の関係は周囲には隠していたし、気づいている者がいたとしても暗部の部隊長の耳にまでそんな噂が聞こえているとは思えない。
「…カカシ先生が上忍師なので、子供たちの元担任としていろいろとお話を伺ったりはしていますが__それが何か?」
「何でも、暗部に戻って来るらしい。理由は判らんが」
「カカシさんが……?」
どくりと、心臓が脈打つのを、イルカは感じた。
next
|