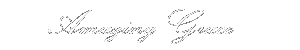
(4)
「……お前は……」
その場に崩れ落ちそうになるのを何とか踏みとどまり、カカシは言った。
「俺がうみのイルカを始末して成り代わったのは、5年前の事だ」
「5年前…」
鸚鵡返しに、カカシは呟いた。
すぐには、言葉の意味が理解できなかった。思考が停止したかのように、頭の中が白くなる。
眼の前にいるのは、『うみのイルカ』の偽者。
そして彼が誰よりも愛した人は、『うみのイルカ』では無く、他里の密偵だったのだ。
煮え滾るような憤りは潮の引くように消え、代わりに虚しさが残った。
あれほど愛した微笑みも、あれほど望んだ温もりも、全てが偽りだったのだ。
「……馬鹿か、俺は」
吐き棄てるように、カカシは呟いた。
その日、あの人は何だか沈んでいた。苛立ちを隠しているようにも見えた。それでも俺を見ると、微笑って『お帰りなさい』と言った。
『今夜は茄子の味噌汁と秋刀魚の塩焼きですよ』
『…どうかしたんですか?』
『秋刀魚は特売で安かったんです。茄子は貰い物のお裾分けに預かったんで。別にあんたの為のメニューって訳じゃありませんよ』
笑って台所に入ったあの人に、俺は背後から近づいた。
『おかずの話をしてるんじゃ無いんです。イルカ先生、どうかしたんですか?』
あの人は怪訝そうな顔で俺を見た。
けれども俺が何も言わずにずっとあの人を見つめていると、幽かに辛そうな表情を浮かべて眼を逸らした。
『俺がどうかしたように見えるんですか?』
『何かがあって酷く苛立ってるって、顔に書いてありますよ』
『何、訳の分からない事、言ってんですか。手が空いてるなら大根おろし作って__』
俺は黙ったまま、あの人を抱きしめた。
あの人は何かを言いかけて止め、俺に軽く身を凭れさせた。
何があったかは判らないが、きっと辛い想いをしているのだろう__そう思うと、抱きしめる事しか出来ない自分の不甲斐なさに腹が立つ。
だが、あの人が何も話してくれないのは仕方が無いのかも知れない。
俺も、あの人に話さない事があるのだから。
任務の機密に拘わるような事は、言うまでも無くお互い、口にしない。だが、俺があの人に話さないのは、そんな事じゃない。
本当は誰よりもあの人に聞いて欲しいと思う。そう願いながら、話せずにいる。
話せば、あの人を傷つけ、苦しませてしまう。
俺は、それが怖かったのだ。
物心ついた時に既に忍なんかやってたせいか、俺はまともな人付き合いってものが出来ないらしい。
それが具体的にどういう事なのかは判らない。
ただ自覚しているのは、自分の弱みを晒すのを恐れているという事。まるで野生の獣が火を恐れるように、俺は他人に自分の弱みを知られるのを恐れる。
相手が無二の親友でも、それは変わらなかった。
もし俺が自分の弱みを晒していれば、オビトは俺を庇って死んだりしなかっただろう。
そんな事をすれば俺は一生、自分を責め続け、毎朝を慰霊碑の前で過ごす事になるのだと判っていれば、オビトはあんな残酷なマネはしなかった筈だ。
イルカ先生に惹かれたのは、よく笑いよく怒り涙もろい情感の豊かさ故だ。
とても忍とは思えない程に感情表現が豊かで、子供が好きで、子供たちに愛されている。
相手が子供でも、見下して『教えてやる』という態度は取らない。一人一人の個性をよく知っていて、可能性を信じている。
頑固なほどにまっすぐな性格で、相手が格上の上忍でも、意見が合わなければ億さず反論する。
裏表が無く、ある面では子供のように純粋で、しっかりと自分を保った芯の強い人。
この人になら、自分の全てを曝け出せる__そんな気がした。そして俺の弱さも醜さも全てを受け入れ、全てを赦してくれるのではないか…と。
だが、俺は甘かった。
イルカ先生を愛しいと思えば思うほど、弱みなど見せられなくなった。
人を殺めた罪悪感に苛まされている癖に、何事も無かったかのように笑って、血塗れた手であの人を抱いた。
俺があの人に弱みを見せないように、あの人も俺に弱みを見せてくれなかった。
幾度となく身体を重ね、肌を交わしても、二人の間にある垣根が取り払われる事はなく、互いの心には、踏み込むことが出来ない領域が残った。
いっそ、俺が自分の全てを晒してしまえばあの人も垣根を取り払ってくれるのでは無いかと思うことも一度や二度ではなかった。
けれども、それは出来なかった。
ただでさえ俺は、あの人の与えてくれる温もりに溺れていた。
この上、弱みなど晒してしまったら、一人で生きて行けなくなってしまう。
俺を捨ててくれればいい。
忘れてくれればいい。
──────アナタの中の俺を殺して下さい。
弱みを晒す代わりに、俺はあの人に別れを告げた。
これ以上、一緒にいても、あの人は俺に弱みを晒してはくれないだろうし、俺もそれは出来ない。
それなのに、還れるかどうかも判らないのに『待っていてくれ』とは言えない。
身勝手な言い分なのは判っている。
結果がこうなる事は、初めから頭のどこかで判っていた筈だ。だが俺は冷静な予想を無視し、誘蛾灯に群がる虫のように、あの人の与えてくれる温もりを求めてしまった。
それが過ちである以上、終わらせなければならない__引き返せる内に。
「……見事に騙されてたもんだな。ナルトや、三代目まで」
「…以前のうみのイルカを知らないあんたが見抜けなくても、恥じる事は無い」
「恥じてなんかなーいよ。ただ、呆れてるだけ」
致死性の毒が既に全身に回っているというのに、暢気とも取れる間延びした口調で、カカシは言った。
『イルカ』は、幽かに眉を顰めた。
「……巻物を渡せ」
「欲しかったら、自分で取れば?」
言ってカカシはへらりと笑った。
ぐらりと視界が揺れ、平衡感覚を失う。
その場に倒れ伏したカカシを、『イルカ』は黙したまま見下ろした。
next
|
|