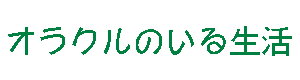
細かな砂がさらさらと落ちるのを、穏やかな雑色の瞳が硝子越しに見つめる。見守るように、優しく。すべての砂が落ちきると、古風な衣装に華奢な身体を包んだその青年は、上品な手つきでポットからカップに琥珀色の液体を注いだ。ふうわりと漂う馥郁たる薫に、青年は満足げに微笑む。 「紅茶がはいりましたよ、Dr?」 おっとりした言葉に、広い部屋の奥まった位置に置かれた机に向かっていた男が顔を上げる。60代半ばのその男の風貌は険しく、近寄りがたい雰囲気に満ちている。が、その冷酷な印象とは別人の様な表情が、彼が声のした方を見ると共に浮かぶ。 「ああ、ありがとう。後で飲むからそのままにしておいてくれ」 「はい、Dr.」 言って、優しく微笑む青年の姿を見れば、男の険しい印象が、一瞬の内に変わったのもうなずける。 「Dr.…!」 ドアが開くと共に、別の男が忙しげに部屋に入って来た。青年は、その男にも優しく微笑みかけ、声を掛けたげに僅かに唇を開いた。が、男はまっすぐに部屋の奥まで進むと、Dr.と呼んだ男の傍らに歩み寄る。そして、何やら小声で話し掛けた。Dr.の方も、険しい表情で何度か頷く。 「…に、間違いは無いのだろうな」 「勿論です。さも無ければ…」 「彼を、危険なめに遭わせる事など__」 「ええ、絶対に…」 男が部屋から出て行くと、Dr.は席を立ち、ゆっくりと青年__正確に言えば、青年の姿をした立体CG__に歩み寄った。 「…何か、あったのですか?」 幾分か不安げに、そして心配そうに、青年が聞く。Dr.は、相手を安心させる為に、微笑して見せた。他の誰にも、決して向ける事はない表情だ。 「お前が心配する事など、何もない。それどころか__」 言いかけて、Dr.は躊躇った。すべては動き出したばかりなのだ。ぬか喜びはさせたくない。もっと言えば、それは自分に対する戒めでもあった。 「…それどころか…?」 Dr.は、立体CGのティーセットに視線を向けた。いかに精巧に造られていようと、所詮はCG。生身の人間である彼は、丁寧にいれられた紅茶を手に取るように見る事は出来ても、その薫や味を楽しむ事は出来ない。 「__嫌…。それより、調子はどうだ、オラクル?」 「はい。とても良いです」 おっとりと微笑んで、青年は言った。その様子に、Dr.は満足げに頷いた。調子が良いのは判っている。10年以上、前に、オラクルを自分のラボに連れて来た日から、常に細心の注意を払って保守(メンテ)しているのだから。 ――思えば、奇妙な事だ。 忠実な懐刀である助手が去り、大切に育てている”養子”のCGが消えると、広い部屋には彼、一人が残った。 ロボットプログラムは、彼にとって、常に最も身近な存在だった。或る意味では、人間以上に。両親も、姉もロボット工学者。彼自身も、いつか同じ路を選んでいた。そうであるにも拘わらず、或いは、そうであるが故に、苛立って来た。ロボットプログラムを、敵であるかの様に見做して来た。 それが嫉妬だったのだと、今では認められる。 両親も姉も、ロボットを愛し、ロボットの研究に没頭していた。それ故に、嫉妬したのだ。相手が、人に造られし物であるにも拘わらず。 ――ロボットでは無いわ。でも、人格を持ったプログラムよ。 そう、姉は言った。そして、哀しげに微笑む。 ――最期の調整が終わったら、閉じ込めなければならないの。と、言うより、外に出る機能は無いのよ。 ――最期の、調整? 辛そうに、姉は眉を顰めた。 ――思考を、調整しなければならないの。さもなければ、心理的負荷が大きすぎてしまうから… ――こちらは私の弟のDr.エリオット・クェーサーよ カシオペア博士の言葉に、三次元CGは戸惑いがちに微笑んだ。 ――始めまして、Dr.クェーサー。オラクルと申します 礼儀正しく一礼してから、カシオペア博士の方を見る。これで良かったのかと、確認するかのように。カシオペア博士が軽く頷くと、青年は、ほっとしたかのほうに、微笑んだ。 ――可愛い… 生まれて初めて、そう、思った。しかも、相手はプログラムだ。ロボットプログラムでは無いからボディも持ってはいない。 だが、”人格”はある。意志と、感情を持っている。 それを特定の空間に閉じ込めてしまうなど、余りに残酷ではないのか…? 全てが、初めての経験だった。誰かを、可愛いなどと思うのも。何かを、残酷だなどと思うのも。そして、鼓動が早い。頬が、熱い。こんな事は、子供の頃に風邪をひいて寝込んだ時、以来だ。あの時、仕事で忙しい母親は側にいてはくれなかった。 気がついた時には、そのプログラム__完成まぢかの<ORACLE>システムの中枢__を、自分のラボに、拉致していた。 あれから10年以上が過ぎた。オラクルの存在は、極秘ではあったけれど、無味乾燥な日々に潤いを与えてくれた。周囲から__実の姉からすらも__冷酷無比な人間と思われ、その仮面をかぶり続ける事は容易な事では無い。だが、ロボット工学者でありながらロボットに嫉妬しているなどと認めたくなければ、そしてそれを人に知られたくなければ、仮面はかぶり続けねばなるまい。 クェーサーは、忠実な助手がもたらした資料を調べた。<ORACLE>は独立した機関であり、アトランダム研究所の総帥である彼ですら、<ORACLE>に関する機密を知る事は出来ない。 が、今、その機密の一端が明らかになった。彼が造ったロボットプログラムが統御し、そのオリジナルであるロボットが守護者であるシステム。それへの、非正規なアクセス方法が明らかになったのだ。 「…ハッキング…?」 戸惑いの表情を浮かべ、オラクルは言った。 「心配する事は無い。ただ、データを取ってくれば良いだけだ」 穏やかに、Dr.クェーサーは言った。側から、ホーンも口添えする。 「君は元々、<ORACLE>の統御者として、造られた。だから、<ORACLE>を制御するなど、簡単な筈だよ」 言われて安堵したのか、オラクルは微笑んだ。 「だったら…大丈夫、かな…?」 クェーサーは、そしてホーンも頬を緩めた。二人とも、そんな表情を他の誰かに見せる事は無い。 「気を付けていっておいで。余り、遅くならないようにな」 「はい、Dr.」 殆ど、1分おきに、クェーサーは時計を眺めていた。気付くと、ホーンも同じ事をしている。そもそもは<ORACLE>の空間内に閉じ込めてしまうのが不憫で拉致して来た。が、知られてしまったら、連れ戻されてしまう。それで結局、この10年の間、クェーサー・ラボのサイバースペースから出す事は無かった。世間知らずのオラクルが別の空間に出るのは、初めての事なのだ。 それには理由(わけ)があった。 この10年の間、クェーサーはオラクルに、ボディを持たせてやりたいと思っていた。そうなれば、オラクルのいれてくれる紅茶を、「後で」などと言わずに味わう事も出来る。その為に、ずっと、研究し、調整を続けて来た。そして、その目的を果たすにはMIRAとSIRIUSが必要である事も判った。極秘データだが、手に入れなければならない。 オラクルを<ORACLE>に行かせたのは、外に慣れさせる為だ。ボデイを得たら、現実空間に出る事になる。が、その前に、他の電脳空間にも慣れさせねばならない。世間知らずで、とても繊細なプログラムであるオラクルに、急激な環境の変化は、強すぎる刺激なのだから。 「…遅いですね」 痺れを切らしたかのように、ホーンは言った。 「<ORACLE>にアクセスして、様子を見てみましょうか?」 「外部とのリンクを切っているのだ。どうやって、アクセスなどする気だ」 幾分か苛立たしげにクェーサーは言った。その時__ 「ただ今、戻りました、Dr.」 プロジェクター上に姿を現したオラクルが、おっとりと言った。ほっとしたのも束の間、クェーサーは眉を顰めた。オラクルの両脇に、別のパーソナル・プログラムがいたからだ。 「ちわーっす。オラトリオ君でーす」 やたらと図体のでかい、派手な外見のプログラムが軽く、言う。もう一方の小柄なプログラムは、反抗するようにこちらを斜めに眇める。彼らが<A−O>と<A−C>である事は、すぐに判った。 「こいつらはどうしたんだ、オラクル?」 威厳を保つ為に黙っているクェーサーに代わって、ホーンが聞いた。 「送って来て貰ったんです。帰り道が危ないからって」 いけなかったのかなとでも言いたげに軽く小首を傾げ、オラクルは言った。 眼鏡の奥で、クェーサーの眼が、冷たく光った。 <A−O>オラトリオはタラシで有名。何の下心も無く、オラクルを送って来たとも思えない。 <A−C>コードは、シスコンで知られる。当然、ブラコンでもある。 迂闊と言えば、迂闊だった。10年前、自分が一目惚れしたように、オラクルに惹かれるロボットプログラムがいても不思議は無い。そしてオラクルに取っては、人間__妖怪だと言う者もいるが__である自分より、他のプログラムの方が、身近な存在なのだろう。 そんな事は赦せない。絶対に。 「外に出たのは初めてだから疲れただろう。今日はもう、休みなさい」 オラトリオとコードが帰ると、優しく、クェーサーは言った。 「はい、Dr.」 言って、オラクルは微笑んだ。この10年以上の間、一度も逆らった事は無い。本当に、素直だ。 「クワイエット達を、呼んでくれ」 オラクルが姿を消すと、クェーサーは言った。別人のように、険しい表情で。 「__はい、Dr.…」 背筋が寒くなるのを覚えながら、ホーンは言った。オラトリオがオラクルの腕に触れ、腰に手を回さんばかりだった事、コードが、オラクルの保護者然としていた事。そのいずれも、Dr.の逆鱗に触れたに違いないのだ。何しろ、オラクルはDr.の大切な”若紫”なのだから…。 「A−NUMBERSは、抹殺されねばならない」 クワイエット達を前に、厳かに、クェーサーは言った。
|
この話を読んでの感想などありましたら、こちらへどうぞ
