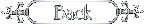|
|
静かに静かに降り積もる。
悲しみが、怒りが、嘆きが…。
ひとつひとつ降り積もる。
静かに、音もなく、まるで雪のように…。
|
「悲しみが攻めてくる…」
ぽつんとつぶやかれた言葉に、オラトリオは振り返った。
まるでごみのかたまりのような大きな雪の欠片に遮られて、従兄弟の姿がよく見えない。
「今、なにか言ったか?」
水気を含んだびしゃびしゃとした雪に濡れないように、オラトリオはオラクルに傘を差し伸べた。
「いや、以前エモーションから聞かされた歌の一節を思い出していた」
オラクルはそう言って、近場のカフェを指差した。
「少し休んで行こうか?」
「ああ、そうだな」
オラトリオは黙って同意する。
取材に行く前から、どんよりと重たい雪雲に覆われていたが、まさか本当に降りだしてくるとは思わなかった。
雪に弱い都心だから、高速も電車も滞り始めている。
タクシー乗り場は、帰宅時間帯を控えて長蛇の列だ。
少しやり過ごしてから帰った方が利口だろう。
気管支の弱い従兄弟を長時間雪の中を歩かせたとなると、叱られるのはきっとオラトリオの方だ。
温かいシナモン・チャイとアメリカン。
それからホットサンドイッチを一皿。
窓際の席に座って外を見ていると、すぐにオーダーされたものが届く。
オラクルがホッとしたように、温かい湯気に微笑んだ。
「寒かったね」
「ああ、まさか本当に降ってくるとは思わなかったぜ」
オラトリオは苦笑を浮かべると、アメリカンを口に含んだ。
「よく、そんな甘いものが飲めるな」
「寒いときには温かくて甘いもの。チャイはあっちの人の知恵の産物だよ」
オラクルは笑って熱そうにカップに唇をつける。
「さて」
とオラトリオは取材メモを開いた。
「今度のは難物かもな。依頼聞いた時は、楽勝だと思ったんだけどな」
「ロボットは今、最も注目されているからね」
オラクルがぼやくオラトリオに苦笑を向ける。
「ロボットを作る人が、必ずしもロボットが好きだとは限らないものなんだな」
溜息を吐き出すオラトリオは、鞄の中から小型テープレコーダを取り出した。
現在彼は、子供向けの雑誌に「ロボット達の新世紀」という対談特集のページを担当している。
ロボットエンジニアリングの分野で活躍する、学者やエンジニアたちから話を聞いて、それを子供たちに向けて分かりやすく噛み砕くという作業だ。
弟たちをその手で育ててきたあなたならお手のものでしょ、と半ば嫌味と共に担当編集者から回ってきた仕事は、しかし発売部数の多い雑誌なだけにオラトリオ的には大歓迎だった。
とりたてて難解な仕事でもなく、これまで回数も順調に進んで全12回連載のちょうど折り返し。
今日は子供たちにも人気の高いエンターテイメント系ロボットの開発者に話を聞きに行った帰りだった。
オラクルは今回の仕事には出番がないので噛んでないが、その雑誌の表紙をよく担当している。
次の表紙の参考にと、オラトリオのインタビューに帯同したのだが、結果として二人は揃って頭を抱えこむハメになっていた。
「ロボットはビジネス以外のなにものでもない、か。大人向け経済誌ならそれでもいいんだろうけど、子供向けなんだよなぁ。どうすっかなぁ」
「アトム・コンプレックスかぁ」
オラクルは苦笑を浮かべて、ホット・サンドに手を伸ばした。
「確かに日本の技術者の人たちはなにかと言うと、鉄腕アトムというけれど、それは世代の問題だと思っていたな。子供の頃の影響ってやっぱり大きいと思うんだけどなぁ」
「それに囚われて、抜け出せないという意見は私には新鮮だったな」
美味しいよ?食べないの?と皿を寄せられて、オラトリオはやっと空腹に気づいた。
「一皿ずつにした方がよかったんじゃないか?」
時計をちらりと見て首を傾げる。
夕飯の支度をして出てきて正解だった。
そうでなければ今頃シグナルから、怒りの腹減ったコールがかかってきそうな時間帯だ。
「ホットサンドイッチ一皿でお前、足りるの?」
くすりとオラクルが笑う。
「まだまだ雪は止みそうにないよ?」
オラクルの言葉に、オラトリオは軽く首を傾げる。
「この間取材でな、美味いイタリアンの店に行ったんだ。この近くにある」
「その言葉を待っていたんだよ」
満足そうにうなずいて、オラクルは話を戻した。
「それで?これまでお前は、『君たちが大きくなる頃までには、人間と同じようなロボットが普通に君たちの隣にいるかもしれない。』と子供たちの好奇心を煽ってきたわけだけど。今日の取材で、あっさりそれが覆された。どうするの?」
「あううう」
オラトリオはその言葉に頭を抱えこむ。
「意地悪だぞ、お前」
「お前の従兄弟なんてやってるからな」
ふふ、と笑って余裕を見せる。
それから彼は、窓の向こうへと視線を移した。
暖かな空調と人の発する温もりで、窓は曇っている。
オラクルはナプキンを手に窓を軽く拭いて、外を見た。
「すごいね。こんなに降る雪を見たのは何年ぶりくらいだろう?」
「俺の心は、まさしく今この外とシンクロしてるね」
溜息を吐き出しながら、オラトリオはぼやく。
「…いいんじゃないかな?ありのままでも」
「え?だって、子供向けだぞ?」
「子供に向けるからだよ。さっきの人だって、子供向け玩具メーカーのロボット開発部門の総責任者だったじゃないか。あえて、ああいうメッセージを出してきたんじゃないかな?」
だってあの人、お前が連載してきたこれまでの回、全部読んでたじゃないかとオラクルは指摘する。
オラトリオは参った、と頭をかき回して長すぎる前髪を全部下ろしてしまう。
煮詰まっている時に彼がよくやる仕種だ。
「確かにな。マスコミが騒ぎ立てる程には、現実のロボット開発の現状は全然進んでない。それはロボット先進国における、この日本において一番顕著だとも言われている。理由は簡単。研究者たちは、あまりにも「鉄腕アトム」にこだわりすぎている」
無意識にポケットから取り出した煙草を、オラトリオはびっくりしたように見て、再びポケットに収めた。
禁煙席である。
灰皿なんてもちろんないのだ。
分かっていても取り出してしまうあたり、今度の仕事は本当にヤバいかも、とオラトリオは苦笑を浮かべる。
「人間と同じ知能を持った、人間とまるで同じロボット、でなければ今頃もっと世の中にはロボットが溢れているかもよ?」
「…そもそも、まだ倫理面が解決してない」
「ロボットが自律的思考を持ち、自ら考え行動して、感情すら持っているとしたら、それはいったいなんなんだろうね」
オラクルは軽く目を伏せた。
「正直、私なら、そんなロボットよりも人間に傍にいてほしい」
「『彼ら』はいずれ気づいてしまうだろうな。自分達は所詮人間の模造品であり、人間ではないのだと」
「それは、とても不幸なことだと思わないか?」
まっすぐ真摯に見つめてくるオラクルの瞳は、何故かオラトリオを落ち着かない気分にさせる。
「…だけど、それを人間の側が勝手に決めつけるのもどうかな?」
「と、いうことをさっきの人も言いたかったんだと思うよ」
あっさりそう言って、オラクルは軽く首を傾げてみせた。
「ちょうど折り返しだ。これまでの連載を見直してみる契機を与えられたんだよ。お前、今回楽しすぎだったしな」
「ううう。オラクル君。お前今、思いっきり他人事だろう?」
「当たり前だろう。それは私のビジネスじゃない」
にっこり突き放して、彼は再び窓の外へと視線を流した。
「でも、おかげで私は、イメージが湧いたな」
「ええっ!?」
お前、それはどー考えても俺への裏切りだぞーとむくれるオラトリオに、オラクルは自慢げに彼を見返した。
「ガラスの巨人だよ」
「は?」
突然なにを言うかと首を傾げるオラトリオに、オラクルは続ける。
「『忘れていたことがある。なにか、悲しいこと。確かにさっきまでは覚えていた』」
軽く節をつけて、歌うまでもなく飛び出したフレーズに、オラトリオは首を傾げる。
大概の歌を網羅しているつもりだが、これは聞いたことがない。
「オラトリオは知らないんじゃないかな?」
お前の趣味じゃないだろうし。聞いていたらある意味びっくり。
とオラクルはそう言って、種を明かした。
「谷山浩子さんっていう女性シンガーの歌だよ。エモーションが昔よく聞いていたのを思い出した」
エモーションは、オラクルの母方の遠縁にあたる。
オラトリオとは、あまり面識はなかったが、両親を亡くしたオラクルはしばらくそちらにいたことがある。
「悲しい歌を聴きたくなかったから、忘れていたんだけど。さっきの人の話と、この雪を見て、思い出した」
悲しそうな光が目に浮かんだのはほんの一瞬。
歳月は心を癒す。
死にたくなるほどの痛くて悲しい記憶はやがて、少しずつ笑って話せる優しいものに変わりつつあった。
「高層ビルよりも大きなガラスの巨人が、深夜の高速道路を楽しそうに歩いているんだ。手に入らないものはなにもないって希望に満ちて。しかし、彼は突然なぜかとても悲しくなる。悲しみが攻めてくるんだ。だから、もっともっと大きくならなければならない。もっともっと巨大にならないと、この突然の悲しみには耐えられない」
オラトリオは目をパチパチとさせた。
「なんか、お伽噺みたいだな。それって歌なんだろう?」
「うん。歌だよ」
オラクルがうなずくと、オラトリオは冷めかけたアメリカンに手を伸ばす。
「で?その巨人はどうなったんだ?」
「どうにも」
オラクルは軽く首を左右に振る。
「歌だからね。悲しみが攻めてくる。だから、早く大きくならなくちゃのリフレインで終わり」
「…なんつーか、お前、それカシオペア家に居候している時に聞かされたわけ?」
「うん。そう」
「あそこのご令嬢も…強気だね」
両親の事故の直後、オラトリオもオラクルもその喪失の痛みからなかなか立ち直れなかった。
様々な苦労と紆余曲折を経て、二人はやっとあの頃のことを話し合える程度に回復している。
「うん。無言の叱咤激励だったんだなって、今、思った」
オラクルは笑って、レシートを手にとった。
「行こう。雪が止んだようだ」
「ああ、そうだな」
オラトリオはうなずいて立ち上がる。
それから、コートの袖に手を通す相棒に笑いかけた。
「ありがとよ、なんか書けそうな気になってきた」
「それはよかった」
「お礼にディナーは奢りましょ」
「やった!ラッキー」
と言いながら、オラクルは手に持っていたレシートをオラトリオに押し付けた。
「え…?ここも」
「もちろん」
にこっと笑ったオラクルに、オラトリオは溜息で返した。
「お前って、本当に強くなったよな」
「当然だろ。悲しみが攻めてくるんだから、もっともっと強くならないと」
「たまには力抜いて甘えてくれると、俺的にはもっと嬉しいんですけど?」
「…考えておくよ」
その言葉を合図に、2人は店を出る。
「あ…」
オラクルは小さな声をあげた。
やんだと思っていた雪は、微かな微かな粉雪に姿を変えて、パラパラと思い出したように空から降りてきていたのだ。
「ほら」
差し出された傘に、自分より10センチ高い従兄弟の顔を見上げる。
「うん」
ひとつの傘の中で寄り添って、オラトリオはぽつりと行った。
「未来に生まれるかもしれないロボット達にも、こうして寄り添いあえる存在があるといいんだがな」
「そうだね…そうすれば彼らも、もしかしたら寂しくはないのかもね」
「…ああ。そうかもしれねぇな」
|
君たち、君たちは自分がなにもので、どこから来たのかを考えてみたことはないかい?
ロボットを作るって、どういうことなのだろう?
特により人間に近いロボットを作るって、どういうことなのかな?
僕たちは、まず自分を理解しないといけない。
人間を知らない人間に、人間のコピーとも言える、人間のようなロボットを作ることは、無理だ。
それでも、君たちが、科学に対して夢や希望を失わないでいてくれたのなら。
ぜひ、君たちの手で君たちの夢を実現させて欲しい。
君たちの知っているロボットを、君たちの知っている形で。
それが人間の形をしていても、していなくても構わない。
ロボットは人間の形をしているものだと、だれかが決めたわけじゃないんだ。
だから、君たちは自由に、君たちだけのロボットのイメージを描いていけばいいんだよ。
|
後日発売された雑誌には、CGで描かれたファンタジックな美しいイラストの隣に、そんなメッセージが加えられていた。
タイトルは「ガラスの巨人」。
高層ビルよりも大きなブリキのロボットが、雪の降る夜空を見上げて泣いている。
その足元では、愛らしい少女が、一輪の花を、泣いているロボットにそっと差し出していた。
|