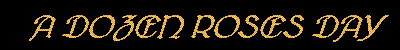|
「手伝うよ」 夕食が済んだ後、一緒に流しに食器を運んで、オラクルは言った。 「俺がやるから座ってろよ」 「だって作るのも全部、オラトリオがやってくれたのに」 そう言ったオラクルの頬を、オラトリオは軽く突ついた。 「酔ってるだろ、お前。グラス、割るぞ?」 「__お前が飲ませるから…」 自覚出来るほど上気している頬に触れて、オラクルは恨めしそうに言った。酔いに羞恥心が加わったのか、白い頬が更に赤らむ。瞳が、幽かに潤んでいる。 「お前、酔うと色っぽいからな」 「……馬鹿」 言うなり踵を返し、オラクルはリビングに戻った。今日は、オラクルのマンションに、オラトリオと二人きりだ。 飲み干してしまったワインのボトルを手にとり、ラベルに目をやる。オラトリオが買って来るのは大概、ドイツワインだ。よく見かけるような甘いタイプの物は避けるが、それでも繊細で果実味があり、酒に慣れていない者でも飲み易い。 つまり、酔わせ易い酒という訳だ。 ボトルをテーブルに戻し、オラトリオが買って来た薔薇の花びらに軽く触れる。 早めのクリスマスを過ごそうぜ そう、オラトリオが言い出したのは昨日の事だ。去年も一昨年も、クリスマスを二人きりで過ごす事は出来なかった。ちびやシグナルが家でパーティをしたがるし、オラクルはカシオペア家に呼ばれたりして、なかなか二人きりにはなれない。だから早めのクリスマスを、と。 それは良いのだが、オラトリオが言い出したのが急だったので、オラクルの方は何も用意していなかった。オラトリオが買い物に行き、夕食の支度をしている間にも、イラストの仕上げをしていた程だ。 それでも、明日の朝まではオラトリオを独占できる__そう思うとオラクルは、身体の奥の熱が増すように感じた。 後片付けを済ませ、戻って来たオラトリオはオラクルの隣に腰を降ろした。 「今日、何とかお前の都合がついて、良かったぜ」 「何か今日でなくちゃいけない理由でもあるのか?」 「Dozen Roses Day」 軽く笑って、オラトリオは言った。 「12月12日__今日は、大切な人に1ダースの薔薇を贈る日なんだそうだ」 オラクルはクリスタルの花瓶に活けた紅い薔薇を見遣った。そして、12本あるのを数える。 「…余り聞かない話だけど。でも…しい」 「でも、何なんだ?」 語尾を曖昧にぼかしたオラクルに、オラトリオが聞いた。僅かに身体を傾け、オラクルとの距離を狭める。 「それならそれで、前もって言ってくれれば良かったじゃ無いか。私も何か用意したのに」 わざと拗ねたように視線を逸らして、オラクルは言った。お互いへのクリスマス・プレゼントはイブまで取っておく事にしたが、ワインも薔薇も料理も、全てオラトリオが準備した物だ。 「今からでも遅くないぜ?」 オラクルの顔を覗き込むようにして、オラトリオは言った。それ程、近くにいても、煙草の匂いがしない。そして、オラトリオが食後の煙草を我慢する理由は、かなり判り易い。 オラクルは、くすりと微笑った。そして、オラトリオの形の良い唇に、軽く触れるだけのキスを落とす。 「…あと、11回」 「__え?」 間近に自分を見つめる恋人に、オラトリオは悪戯っぽく笑った。 「1ダースの薔薇のお返しに、1ダースのキスを」 「…バースディ・ケーキの蝋燭じゃあるまいに」 言いながら、オラクルはオラトリオの頬にキスした。次は耳朶に。 「どういう喩えなんだ、それ」 「オラトリオって、妙に子供っぽいところがあるんだから」 くすくすと笑いながら、オラクルはキスを続けた。額に、こめかみに、閉じた瞼に。 「そこが可愛い__だろ?」 「…馬鹿…」 顎に、そして首筋に口づけてから、オラクルは困ったように、相手を見た。 「話し掛けるから、数が判らなくなったじゃないか」 半ば拗ねたような、同時に甘えるような口調。潤んだ瞳。眼の焦点が合っていない。かなり酔いが回って来たらしい。 「__うわ…」 不意に抱き上げられ、オラクルは思わずオラトリオにしがみついた。 「そんじゃ、最初からやり直し。お返しのお返しも含めて…な」 オラクルの唇が何か言いたげに動いた。が、すぐにそれは優しい微笑に変わった。 大切な人に、1ダースの薔薇を
|